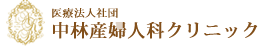不妊検査
妊娠が成立するまで様々な段階がありますがどれか一つが欠けても妊娠が困難になります。原因はご夫婦ごとによって異なりますので、まずは検査で原因を解明することで患者様に合った治療方法を計画します。
基礎体温
毎朝目覚めた直後に体温を測定し、基礎体温表に記入していきます。
黄体ホルモン(プロゲステロン)分泌の変動により通常約2週間毎に体温の上昇、低下を繰り返すので、そのサイクルから卵巣機能の状態や排卵日を推定します。
経膣超音波検査
プローブを膣内に挿入し、超音波により子宮や卵巣の様子を観察することができます。
子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮腺筋症、子宮奇形、卵巣嚢腫等がわかったり、卵胞の大きさや子宮内膜の厚さを計測します。簡便かつ詳細な情報が得られるため、最も頻度の高い検査です。
子宮卵管造影
造影剤を子宮口から注入し、レントゲン撮影を行います。造影剤は白く写るので、流入した様子で子宮の形態や異常、卵管の通過性を調べることができます。この検査後は卵管の通りが良くなるため、妊娠しやすくなるとも言われています。
精液検査
不妊症といえば女性側の原因と見られがちですが、近年男性側による原因も増加傾向にあります。精液の所見によって今後の治療内容も変わってきますので重要な検査です。検査の際は当院またはご自宅で専用のカップで精液を採取していただき顕微鏡で観察します。液量、精子濃度、運動率、奇形率等を調べます。以下、世界保健機関(WHO)基準値を記しています。
各ホルモン値
月経周期は各種ホルモンによって綿密にコントロールされています。月経開始3~5日目に採血しホルモン値を測り、正常に機能しているかどうかを調べます。